①あらすじ
世界初の先物取引所で繰り広げられる、享保の知られざる米騒動――大坂商人vs.将軍吉宗。究極の頭脳戦の行方はいかに!?
時は江戸時代、天下の台所――大坂堂島には全国から米が集まり、日々、値が付けられ膨大な取引がされていた。特に盛んだったのが、先々の米価を扱う先物取引(デリバティブ)。商人たちは紙と筆と頭脳を用い、利鞘の多寡で泣いたり笑ったり。
一方の江戸では、将軍吉宗はじめ、幕閣たちは忸怩たる思いを抱いていた。米価の変動はすなわち武士の年貢収入の変動であり、あろうことか、それらを商人たちが汗もかかず、意のままに決めている。そんな不実の商いは許すまじ、と堂島を支配すべく動き出すのだが……。
市場の自治を守らんとする大坂商人たちと、武士の誇り(とお金)を懸けた江戸幕府との究極の頭脳戦!
※Amazonの商品ページより引用しております。
②読んだきっかけ
今年、門井先生の『札幌誕生』を読んで、開拓していた頃の札幌の風景が見えるような気がするほど没入できた体験に味をしめて、新作が店頭に並んでいたので購入。
今度は吉宗。パチスロとかのイメージや、享保の飢饉、享保の改革などなどイメージが米将軍というくらいしかない私。
その吉宗と大阪の商人がバトルするって面白そうじゃね?というか、デリバティブ?先物取引?どういうこと?と思いながらレジにいきました(笑)
③感想・レビュー
大阪がなぜ天下の台所と呼ばれたのか?
この時代、米をどうやってお金にいたのか?
歴史の教科書や授業で出来事だけ教わってほぼ素通りするような吉宗の享保の改革。
こんなこと考えたことなかった。
これが、読む前の私。
読んでみて、今の株だったり、先物取引だったりをこの時代にやっていたのか?というのが読みながら思うのですが、そういえば、確かに、1石が人1人を1年間養える米の量というのですが、米をそのまま物々交換していたのではなく、貨幣も流通していた江戸では当然、米を貨幣に換える必要がある。
その米をどうやって貨幣に換えるのか
ここに、大阪が天下の台所だと言われていた所以があるということに気づかされます。
そして、吉宗が自分の家来である旗本たちを食わせるためには米の価格が高ければ高いほどよい。理由は米の価格が高ければ高いほど、家来の財布が潤うから。
とはいえ、じゃあべらぼうに高くするためにお触れとか命令で米価を吊り上げるわけでもなく、大阪の商人から財産を没収するなど暴君みたいなことは吉宗はせず、ある意味大阪の商人と真っ向勝負に出るというのが本作品です。
今も昔も米価が大事
という帯にもあるように、当時の米価って大事だよなぁと気づかされると同時に、大阪の商人VS幕府のやり取りを通じて、勉強になるそんな作品だなと思いました。
④こんな方にオススメ
・日本初の先物取引について興味がある方
・江戸時代の武士はどうやってお金を得ていたかということに興味が湧いた方
↓『天下の値段 享保のデリバティブ』はこちらから購入いただけます。
 |
新品価格 |
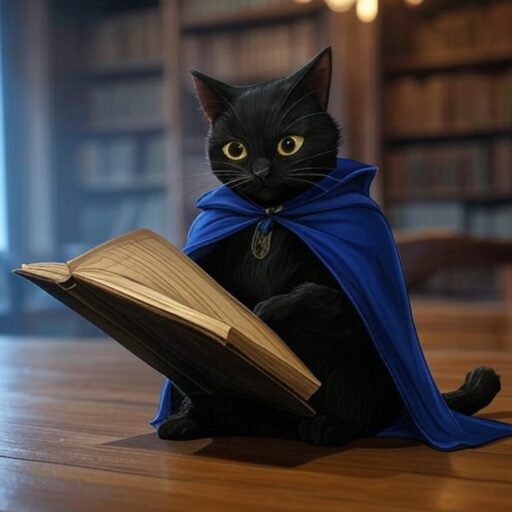
コメントを残す